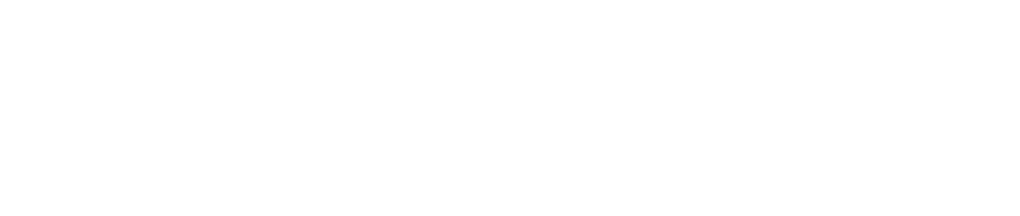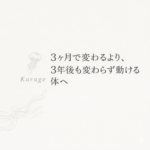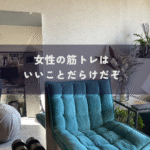〜自分を見つめる力、子どもから教わること〜
先日、幼稚園に通う次女が、いわゆる「トラブル」を起こしました。
今まで見たことがないような姿──
保身のための嘘、お友達にとっては悲しい行動、
そして、トイレに流してはいけないものを流してしまったこと。
私は正直、憤りとショックを感じました。
「どうしてこんなことを…?」と。
でも、そこで本当に私が向き合わなければならなかったのは、
“何が起きたか”ではなく、“なぜ起きたのか”ということ。
最初、私は「お友達がかわいそうだよ」「先生困っちゃうよ」と、
他人の気持ちを優先した言葉ばかりを口にしていました。
それはきっと、娘の中にある「本当の気持ち」を閉じ込めてしまう言葉だったと、後から気づきました。
大切なのは、「なぜ、そうしたのか」。
私は娘に謝りました。
「あなたの気持ちを聞く前に、決めつけてしまってごめんね」
「本当は、どんな気持ちだったの?」
娘の答えは、思いがけず純粋でまっすぐなものでした。
「お友達を楽しませたかったの。びっくりさせたかった。マジックみたいなことがしたかったの。」
「トイレに流したらどうなるか知りたかったの。」
好奇心、驚かせたいという遊び心、
そして、何かを試してみたいという強い想い。
そのすべては、本当に素晴らしい“生きる力”だと感じました。
ヨガの教えに「サティヤ(正直)」という言葉があります。
それは、誰かに正直でいることだけではなく、自分の気持ちにも正直であること。
私自身がそれを忘れて、“母親としてこうあるべき”という固定観念に縛られていたのだと思います。
また、「アヒムサ(非暴力)」の視点からも、
怒りや評価で子どもを押さえつけるのではなく、心に優しく寄り添うことが本当の意味での“育てる”につながると感じました。
私は娘に伝えました。
「あなたがやってみたい気持ちは、すごくいいことだよ。でも、お友達のもので試すんじゃなくて、自分のことでやってごらん」
「怒られることも、経験だから。それも学びになるよ。でも人のものや幼稚園のものは壊してはいけないよ。」
子どもは、自分なりの想いを持って行動している。
それを“悪いこと”と切り捨てる前に、その奥にある気持ちに目を向けること。
その上で、やり方が違っていたら、他の提案をすればいい。
今回のことを正当化するためではなく、間違っていたことは間違っていた。でも子どもにも気持ちがある、ということ。
そして、たとえ何があっても、私は我が子の味方でありたい。
“嘘をつかないこと”を信じるのではなく、
その出来事の裏にある気持ちや意図が、きっとあると信じる。
その信頼関係があるからこそ、話し合い、共に成長していける。
子どもから学ぶことは、本当に多い。そしてきっと彼女も今回のことで多くのことを学んだと思う。そして彼女なりに考えたでしょう。
お友だちの気持ちも、自分の気持ちも、周りの大人の気持ちも。
私たち大人が視野を狭く子どもの世界を守ってあげたいと思いました。
そして、そのプロセスを一緒に考えてくれる家族や友人がいてくれることもまた、ありがたいこと。
ヨガとは、マットの上だけでなく、日常の中にある“気づき”そのもの。
今日もまた、子どもたちからも学び、私も一歩、前に進みたいと思います。